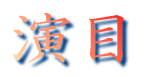
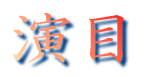
雄勝法印神楽には以下の演目が伝わっている。
初矢
天の御中主の舞で天地創造の舞です。すべての舞の基本となっており私もみっちりとしこまれました。
両天
国生み国造りの神話から仕組まれています。
三天
天の御中主、タカミムスビ、カムミムスビの造化三神の舞
四天
国生み国造りの舞でイザナミ、イザナギの二柱は協力して日本の国を生み、その国を治めるべき神々を生みました。
二柱の神は日本の自然を割り出して一年を360日とし、東西南北と春夏秋冬を定め、まず、東方を春として90日は天合尊の主領、西を秋として90日は天八百日尊の主領、南方を夏として90日を天三下尊の主領、北方を冬として90日は天八下尊の主領と定め、この四神が協力して四季が安定し、日本が栄えてゆくという舞です。
この四神が登場する神楽は他に、所望分と醜女退治があります。
岩戸開
本神楽の中でもっとも重要で必ず舞うことになっている神楽です。神話の天岩戸と同一の内容です。
本編に登場する、天津神国津神の舞は荒型舞の基本の舞方になっているような気がします。
(画像:岩戸開)
五矢
天照大神に反抗して高天原を追放されたスサノウの尊は手足の爪を抜かれ自分がわがままであったことに気づき悔いながら毎日苦しい旅を続けました。良い神になって人々を救い今までの償いをしようと諸国を巡っているうちに行けども行けども人家はなく何も食べず空腹の内に日が暮れはじめ困り果てたとき二軒の民家を発見しました。一軒は見るからに豊かそうな趣の家でもう一軒はとても貧しい様子でした。二軒は兄弟で豊かな方は巨旦といい貧しい方は蘇民といいました。はじめに巨旦に宿を乞いましたが、ぼろぼろの出で立ちのスサノウを見て断ってしまいました。蘇民は尊を迎え入れ粟飯を馳走し、布団もないので粟殻をしいて休ませました。
そのもてなしに感動したスサノウは色々な知恵を授けました。教えにより蘇民は日に日に豊かになり一方巨旦は落ち目になりその土地を去っていったそうです。「情けは人の為ならず」ということを舞っているそうです。
魔王退治(魔王責め)
スサノウの尊が諸国を巡っているうちに、あるところに魔王が魔物どもを率いて出没し生業ができず苦しんでいる住民をみてそれらを成敗して安住楽土を築いたという舞です。
所望分
イザナギ・イザナミ 二柱の神は東西南北、春夏秋冬を定め一季を90日つづと定めてそれぞれの神に持たせていたが、その中に土の神の受け持ちがないので土地はどんどんやせて行き万民は困り果てていました。
そこで、土の神ヤソヨロズタマの命は土の徳を回復するために自分にも受け持ちを分けてくれるよう四人の神に願ったが聞き入れてもらえなかったので、争いによって奪うこととしたため、土地はますますやせ衰えてゆきました。
そこで、万物を司るアメノミナカヌシ(修験道では元気神)が現れて五人の神の仲裁に入り、一神につき90日のうち18日ずつをヤソヨロズタマの命に分け与え、それぞれの季節の境目に入れて土用と名付け春夏秋冬の境目も明確となり土勢も盛り返したということを舞っています。
四神のそれぞれのカンナギが似通っていて間違いやすいので、新人泣かせです。
道祖
猿田彦の舞です。
天孫ニニギの尊が天照皇大神の命令を受けて日本の主となるために降臨する際、アメノヤチマタといわれる道が四方八方に分かれているところにきました。猿田彦はその道にたっていてニニギの尊が迷わず目的地に着くよう道案内をしたそうです
地舞としては最高の舞で、神楽通の見る神楽といえるそうです。
初矢、四天をしっかり覚えてないと泣きを見ます。カンナギが長いです。特徴として、米をまきます。
日本武尊
日本武という呼び名は神代の武人ということで、人皇第11第景光天皇の皇子「小うすの尊」の物語を舞にしたものだそうです。
尊に恨みを抱く女が岩長姫になりすまし、熱田神宮に忍び入り天の叢雲の剱を盗み出し、その罪を尊に着せようとしました。このことを知った尊は非常に怒りました。実はこの女は大海原に住む悪鬼であることがわかり、見事退治し、宝剣を取り戻すという、荒型舞の代表的舞です。
人気がある舞いで、よく舞われます。
醜女退治
演目の四天で登場する木の神、金の神、水の神、土の神がそれぞれの特徴や自慢話のしているときに、火の神がくわわってこそ万物が栄える事に気づき醜女が火の神の化けて四人を苦しめました。そこへ塞の神が醜女を追って出て四神を守り醜女を退治するという舞いです。四天と違い四神は道化の面を使用をします。
蛭児
西の宮の祭神の舞です。鯛釣りとか恵比寿舞いなどと呼ばれておりこの舞いで使用した鯛の切り子は大漁充満商売繁盛の縁起ものとされ、漁師町ではその切り子を貰うと行列をなします。
笹結
二柱の神が作った国土「オノコロ島」、即ち日本に五鬼大神という悪鬼が住み着き良民を苦しめた為、田中明神がこの悪鬼を退治するという舞いです。舞台をおりて、ところ狭しと舞う非常に動的な神楽でありながら、舞いの基本となる動作のうち、荒型の出掛かり、鈴御神楽、戦い、と構成内容は比較的難易度の低い構成となっており新人はよくこの舞いを舞うよういわれる。結構客受けがいいので、私は好んで舞わさせてもらっています。但し、結構つかれます。
橋引
簡単に説明すると、川に橋を架けようとしましたが、うまくいかず、神様に祈願したら、近くに住む女に有馬明神の社の境内にある、伊会杉という見事な杉三本を伐採し、使用すればうまくいくとのお告げがありそのとおりにしたら見事橋を架けることが出来たという舞いです。子供たちに非常に人気があります。
釣弓
ご存じ海幸彦山幸彦の物語です。雄勝法印神楽の中でもっと長時間を要する神楽で今はほとんど舞われません。しかし、現在舞える人がいなくなったわけではないので、是非習得したい神楽の一つです。
産屋(火々出見)
彦火々出見の尊が豊玉姫と結婚し、身籠もりその子が男であれば日本の王となる者なので本土で生むように約束しました。
産み月となったので、姫は本土に渡ってきたので、尊は喜び鵜の鳥の羽で産屋を作りました。
豊玉姫は決して産屋の内を見ないでくださいと言い渡し産屋へ入っていきましたが、どうしても気になり尊は産屋を覗きました。
すると姫はその姿はなく龍神蛇体となり、玉のような男の子が生まれていました。尊は産屋を打ち破り皇子を救ったという舞です。
空所
天御中主の神が天と地を定めた時の舞であるようです。
個人的に結構好きな舞で静と動のバランスが気に入ってます。
地舞+二還胴っといったかんじです。
中途半端な時間を利用して舞ったりします。
順唄
男神と女神が登場し夫婦和合の舞を舞う神楽です。
夫は妻を、妻は夫を崇拝する心から織りなされる優雅な舞です。
最近の動的神楽がもてはやされる中に、しっとりと舞うこの神楽が私は好きですが、ここ10年位披露してません。
叢雲
ご存じ八岐大蛇を成敗する舞です。準備が大変なので昭和の終わりから平成13年まで舞うことがなかったのですが
雄勝でおこなわれた神楽大会にあわせ、見事に伝承できました。今では、2年に1回は奉納しています。
白露
白露と順唄がおなじなのではないかと言う説がありますが、一応別物として伝承しています。
確かに微妙な違いしかないんです。
鬼門
俗に綱切り舞といわれ、ほとんどの地区で奉納されます。
目に見えない災いを断ち切る舞で、昔は厳重過酷な修行をなし終えた法印のみ舞うことが許されたそうです。
色々な寅が入り複雑で、地舞・荒型の双方を極めなければ舞えない神楽です。
張った綱を切るところだけ一般うけしますが、そこにたどり着く課程が実はかっこいいと思います。
荒神舞
火は平和に大切に利用することによって大きな恵みとなるが,悪用したり粗末に扱うとすべてを焼き尽くしてしまいます。
この舞は火の神 カグツチ,またの名をホムスビといい,自らをおさめる鎮火と火防の霊力を舞に表現したものです。
最近はあまり舞われませんが,昔は新築祝いなどでよく奉納されたそうです。
普照
岩戸開の立役者天児屋根の命の舞です。
宇賀玉
外宮,豊受神・保食神,稲荷神の舞です。この神楽は五穀の種をまいて食料を確保しようとがんばっているとこに魔王が現れ五穀豊穣の宝物を農民より奪い取ってしまいました。これにより不作続きとなり困っているところに保食神が農民の姿で現れて酒を飲ませたりして,見事取り戻したというお話です。
二の矢
山の神舞とも言われています。安産祈願の舞です。
湯の父
天児屋根の命の舞です。日本の国生み,国造り古事を語る舞です。
国譲
獅子